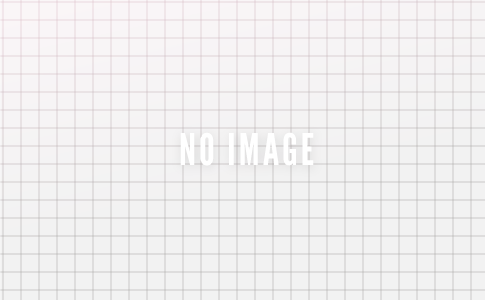※2018年2月1日発行の1級キャリア技能士試験対策メルマガ2017よりの抜粋記事です。
【1】相談者がメンタル不調などの疾病を抱えていたら
今回の3ケースの中で、ケース1の相談者が「発達障害」ではないかというご質問をよく受けます。
そもそも「発達障害」の判定をするのは医者であり、その医者も判定するには困難を極め、医者によって診断が下る場合もあれば、そうでない場合もあります。
メンタル不調による疾病名は、ほぼ本人が訴える症状で決まります。
血液検査やCTなどで明確に決まるものではないからこそ、診断が難しく、治療も難しいのです。
ここで私がいいたいのは、相談者が落ち込んでいたり、休みがち、疲れている、コミュニケーションがおかしい、仕事に優先順位をつけられないなどの事象があった場合、「疾病性」にとらわれるのではなく、「事例性」という実際に起きている事実に焦点を当てることを忘れないでほしいのです。
ケース記録に病名が書かれていたとしても、それは相談者が医者の診断によってくだされたものでなければ、相談者や、その周囲、あるいは事例相談者の決めつけや思い込みである域を超えません。
たとえ、医者の診断が何かくだっていたとしても指導の焦点は、そこにはないでしょう。
キャリアコンサルタントの指導試験ですから、疾病についてはリファーするということがあるにしろ、疾病に対して、何か配慮するとか、そこに対応していないことが指導のポイントにはならないと私は考えます。
【2】事例指導の鍵は関係構築
事例相談者と受検生であるあなた(指導者)は何よりも最初に信頼関係を作ることを意識するでしょう。
しかし、関係構築は仲良くなることだけではありません。
相手の要望は何かを的確につかみ、そこに応えることこそ関係構築の神髄です。
30分の中で後半指導に入ったとき、あなたがSV(指導者)目線で指導をしたとしたら、事例相談者(CC)は自分の話を聴いてくれて理解してくれないと感じ、関係性は崩れる可能性大です。
だからこそ、ケースにある【キャリアコンサルタントが相談したいこと】を無視してはいけません。
指導において、何よりも、CCが相談したいことに応えるのが優先です。
CCが相談したいことには、
・対応に何が不足していたか
・次回の約束にこなかった理由を知りたい
・次回の面談をどう進めるといいのか
・何が悪かったのかわからない
ということが多いです。
この点に指導者として解決策を提示することが何より、事例相談者を動機づけることになります。
【3】質疑応答の苦手な方へ
ロールプレイが終わったあとの質疑応答が苦手という方がかなりいます。
頭が真っ白になって、何も考えられなくなるという人もいます。
それを防ぐためには、まず、質疑応答で何を質問されるかを
あらかじめ認識しておくことです。
想定される質問として、
・30分の指導ロールプレイを振り返って、良かった点・改善したい点は何ですか
・この事例相談者の課題(あるいは事例の進め方の問題)は何ですか
・事例相談者の問題を事例相談者に気づいてもらうために(共有する)どのようなはたらきかけをしましたか
・今回の指導で出来なかったことを改善するためにどのような研鑽を積んでいきますか
などがあげられます。
これらに答ええられるように準備してください。